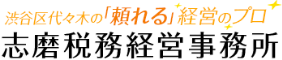確定申告を電子申告で行うメリット・デメリットを解説
確定申告は、所得税や消費税などを正確に計算し、税務署に申告する重要な手続きです。
近年では、電子申告(e-Tax)を利用することで、従来の紙ベースの申告に比べて簡便に行える方法が普及しています。
しかしながら、電子申告には利便性だけでなく注意すべき点も存在します。
この記事では、確定申告を電子申告で行う際のメリットとデメリットを詳しく解説します。
e-Taxとは
e-Taxとは、国税電子申告・納税システムの略称で、国税に関する申告や納税をインターネットを利用して行うことができる仕組みです。
国税庁が提供しているサービスで、確定申告のほか、各種税金の納付、申告データの確認など、さまざまな手続きを電子的に行うことが可能です。
電子申告のメリット
ここからは、電子申告の主なメリットについて解説していきます。
手続きが簡単で効率的
電子申告では、自宅などからインターネットを通じて申告を行うことができます。
わざわざ税務署に足を運ぶ必要がなく、時間や交通費を節約できる点が大きな利点です。
また、電子申告は入力した内容に基づいて計算を自動的に行ってくれるため、計算ミスが減り、申告手続きの効率化につながります。
添付書類の省略が可能
紙ベースの申告では、医療費控除の明細書や各種保険料控除の証明書などを添付する必要がありますが、電子申告では多くの添付書類が省略可能です。
ただし、税務署から求められた場合には提示が必要なため、法定申告期限から5年間は手元に保管しておく必要があります。
この求めに応じない場合、これらの書類は確定申告書に添付または提示されていないものとして扱われる可能性があるため注意が必要です。
e-Taxを利用した場合に省略できる主な添付書類は以下のとおりです。
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・医療費控除の明細書
・医療費通知(医療費のお知らせ)
・医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)
・セルフメディケーション税制に係る一定の取組を行ったことを明らかにする書類
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
青色申告者は控除額が10万円増額する
2020年度以降に電子申告で青色申告した場合、控除額が55万円から65万円に増額します。
還付がスピーディー
電子申告を利用すると、還付金の処理が紙申告よりも早く進む傾向があります。
紙申告の場合は、おおむね1か月から1か月半程度の期間を要することとされていますが、電子申告3週間程度で還付を受けることができるとされています。
ただし、申告内容が誤っていたことなどで再提出した場合は、電子申告した場合でも上記期間で処理されないことがあります。
申告内容の管理が容易
電子申告で提出したデータは保存されるため、過去の申告内容を簡単に確認することができます。
これにより、将来の申告作業がスムーズになり、特に毎年申告が必要な場合には便利です。
電子申告のデメリット
続いて、電子申告の主なデメリットについて解説していきます。
利用環境の整備が必要
電子申告を行うためには、インターネット接続環境や利用者識別番号の取得、マイナンバーカード、ICカードリーダーなどが必要です。
これらの準備段階で、ハードルが高いと感じる人もいます。
システム障害のリスク
電子申告はインターネットを介して行われるため、システム障害や通信エラーが発生する可能性があります。
申告期限直前にトラブルが発生すると、期限内に申告を完了できないリスクがあるため、早めに手続きを進めることが重要です。
電子申告を始めるための準備
電子申告を始めるために必要な準備について解説していきます。
必要な準備
電子申告を始めるには以下の準備が必要です。
・マイナンバーカードか電子証明書
・ICカードリーダー(マイナンバーカードなど ICカード式の電子証明書を利用する場合)
・インターネット環境
・利用者識別番号
利用者識別番号の取得
事前に、税務署へ「電子申告・納税等開始届出書」を提出し、利用者識別番号を取得する必要があります。
この手続きはオンラインでも可能です。
まとめ
電子申告は、利便性や効率性の向上など多くのメリットを持つ一方で、準備や操作に一定の手間がかかる点には注意が必要です。
自身の環境に合った申告方法を選ぶことが重要ですが、不安や疑問がある場合は税理士に相談することを検討してみてください。